テーマは日本の歴史の流れと、観光を結びつけることで、旅をおもしろくしようという取り組みです!あたりまえのことではありますが、日本の歴史の主要人物と歴史ある寺社仏閣は様々な関係性で繋がっています。
歴史は時代と時代を分断せずに、流れで見るとよりおもしろく感じられます。時代の流れの中で、多くの寺社仏閣が生まれています。現地でそのことに想いを馳せることで旅に浪漫が生まれます。
※歴史解説がメインではないので、簡単に流れをまとめています!(諸説ありでよろしくお願いいたします。)
承久の乱勃発
1219年 これまで後鳥羽上皇と密接な関係を築いてきた将軍実朝が暗殺されます。
後鳥羽上皇は、信頼する実朝が殺害された知らせを受け、失態を犯した幕府に対し強烈な不信感をもつのです。
また後鳥羽上皇はこの混乱の原因が、執権の北条義時にあると考え、義時に対し敵意をもつようになります。
後鳥羽上皇は幕府がまとまらない間に、荘園(私有地)の権限を拡大しようと、一部の地頭(土地や税収を管理する役)を罷免するよう幕府にせまります。この混乱に乗じて幕府の弱体化を図ったのです。
この命に対し北条義時は〝頼朝公が任命した役は理由なく解任できない〟としてはねつけます。
1221年 仲恭天皇の命として〝北条義時追討の命〟が下されます。これは倒幕ではなく、北条義時の謀反に対するものとし、天皇の権威を忘れ、傀儡の幼将軍を思うがままに操る北条義時の謀反と断罪したのです。
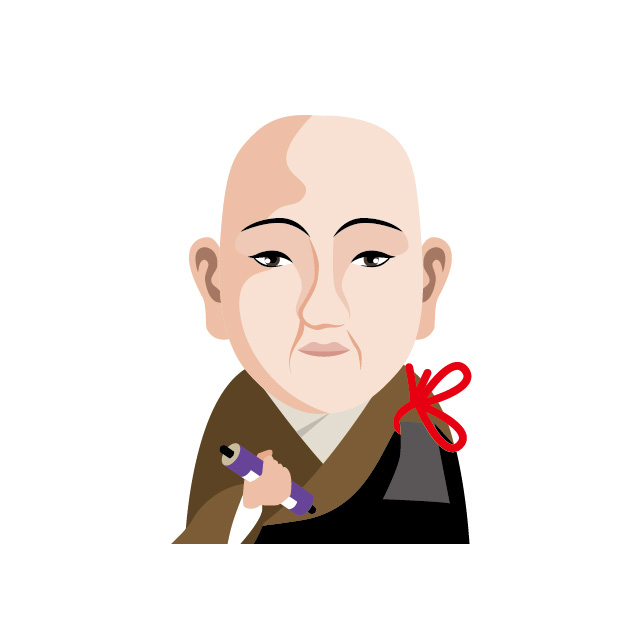
一方、鎌倉幕府では幕府首脳陣による対策会議が開かれていました。幕府は徹底的な情報封鎖を行い、御家人間に追討命が広まるのを防ぎ、さらに御家人たちに尼将軍政子が熱烈な演説を行います。
〝頼朝の恩は山よりも高く、海よりも深い。道理から外れた命に従わず、源氏三代の将軍が残したものを守りなさい〟
当初朝廷と戦うことを決意した幕府は、守りを固めて朝廷軍を迎え撃つことを考えました。
しかし宿老の大江広元(おおえひろもと)は、源頼朝以来の戦の経験から長期戦になると敵勢力が増えると考え、短期決戦に活路を求めます。
尼将軍政子と北条義時はその意見を受け入れ、嫡男の北条泰時(ほうじょうやすとき)を総大将とし、源氏一門(足利氏等)とともに少数の軍勢で京へ出撃させたのです。
この戦は、北条義時が後鳥羽上皇の無理難題から御家人を守ったことが一因であるため、挙兵で義時の名声は大きく上がります。
幕府を支持する多くの御家人が加わり、幕府軍は一気に膨れ上がっていきます。そして圧倒的な19万の大軍勢となり京を攻めるのです。
後鳥羽上皇はまさか幕府軍が攻めてくるとは思いもよらなかったのです。朝廷に付いた西国御家人(近江守護佐々木氏、大内氏等)の軍勢は出兵して宇治川で幕府軍と対峙します。
しかし幕府軍は決死で宇治川を渡り、朝廷軍を打ち破り京を制圧したのです。この戦後後鳥羽上皇は隠岐中ノ島へ流罪とされます。後鳥羽上皇は中ノ島で仏への信仰と和歌を詠む日々を過ごされ、京に戻る事はかないませんでした。
なお、この戦で活躍した源氏一門足利氏は、京と鎌倉の中間の重要地点、三河を領地として与えられます。三河の足利氏は地名の吉良氏や今川氏を名乗ります。さらに足利氏は代々北条氏から正妻を迎えて、大いに発展していくのです。
承久の乱後、朝廷が持つ領地や権限はすべて幕府に奪われ、朝廷は幕府に従属することになります。
そして京に鎌倉幕府の出先機関が設置されます。六波羅の北と南に六波羅探題が設置され、北条義時の嫡男泰時と、弟時房を京に駐留させて朝廷を監視するのです。
北条義時の死と後継者争い
鎌倉幕府を主導する執権 北条義時(ほうじょうよしとき)は、承久の乱が終結した三年後に亡くなります。
死因は病とする説、また承久の乱の恨みによる暗殺説、妻(伊賀の方)による毒殺説などがあります。
この頃には北条氏の執権体制は確立され、義時の後は嫡男北条泰時(ほうじょうやすとき)が継ぐことになります。 (執権とは北条氏が世襲する鎌倉幕府の要職で、幕府将軍の補佐役として政治を主導する立場にあります。)
1224年 北条泰時の相続に対し問題が発生します。泰時の義理の母である伊賀の方が、自身の娘婿(一条氏)を幕府将軍にし、実子の政村(まさむら=義時の五男)を執権につかせようと謀ったのです。
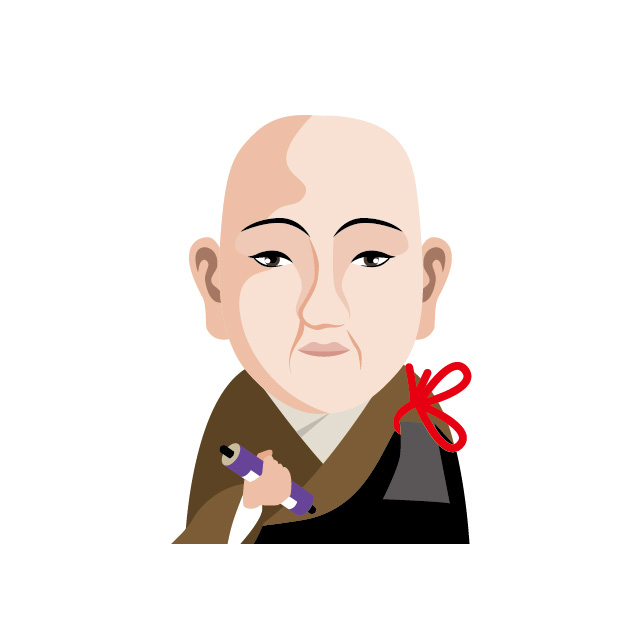
この危機を察知した尼将軍の北条政子(ほうじょうまさこ)は、加担していた大豪族三浦義村を説得し、計画から離反させてこの計画を潰したのです。
(その後伊賀の方は伊豆に流罪にされ、しばらくして亡くなります。)
計画の中心にいた三浦氏は鎌倉御家人の名門で、古くから源氏に従い源頼朝 旗揚げの際から支援してきた、三浦半島を本拠地とする大豪族です。
北条政子はこのような事態になったことを憂い、今後北条一族が分裂しないよう、嫡男泰時以外の兄弟を分家扱いにします。
この時から北条氏は執権を継ぐ本家と、それを補佐する分家に分かれたのです。そして次男朝時(ともとき)は、祖父 北条時政の館があった名越(なごえ)を名乗らせ、一族の中で本家に次ぐ高い家格とします。
(その他の分家に極楽寺流・金沢流・赤橋流・政村流 等があります。)
北条泰時の政治

1225年 尼将軍 北条政子が病にかかり亡くなります。また政治の最高職を務める大江広元(おおえひろもと)も同時期に亡くなり、幕府は政治の中心人物を同時に失ったのです。
鎌倉幕府は 最高貴族 藤原氏から迎え入れた、三虎(みとら)を元服させて四代将軍に就任させます。四代将軍 藤原頼経は源頼朝の姉の孫にあたり、遠いとはいえかろうじて源氏一門の血縁といえる人物です。
また幕府を支えた二人が亡くなる難局に対し、北条泰時は集団指導制・合議政治を取り入れます。まず執権を二人体制(一人は副執権)で行う連署としてこの制度が定着します。
また評定会議を行うようになります。これは執権2名と、幕府重鎮三浦義村他評定衆11名の計13名で行うもので、鎌倉幕府の最高機関に位置付けられます。これは先代からの十三人の合議制をもとにして生まれた制度です。
1232年 新政権がスタートして北条泰時は御成敗式目を制定します。これは武家政権の鎌倉幕府のために作られた日本初の武家法です。
1221年の承久の乱(後鳥羽上皇と執権北条義時の対立)以降、京の朝廷が持つ政治的権限を大幅に制限したため、鎌倉幕府が朝廷に代わって国家を統治するための規範(判断や評価をするの為の基準)が必要になっていたのです。
この武家法は守護の治安維持や地頭の年貢の徴収と管理、また貴族や寺社・現地住民との間に起こる紛争や法的トラブルを、公正に解決する基準を定めたもので、問題をスムーズに解決し、守護と地頭の権限を明確にする事に役立ちました。
1238年 四代将軍 藤原頼経は京に上洛します。この時、執権北条泰時と三浦義村が同行しています。(この頃には四代将軍 藤原頼経と三浦氏は親しい間柄にあったとされます。)
この上洛は泰時と義村にとって生涯の晴れ舞台となったのです。
北条泰時はこの時、京の貴族たちとの関係を構築しますが、倒幕派の公卿と天皇の皇位継承で対立し、倒幕派の筆頭である九条家(藤原氏)との関係に亀裂が入ります。これは後に大きな問題をもたらす事になるのです。
1239年 幕府の宿老(経験が豊かで物事に詳しい長老)三浦義村は急死します。脳卒中によるもとされますが、世間では後鳥羽上皇の呪いではないかと噂されました。
鎌倉大仏の建造
北条泰時は晩年になって民間主導で進められていた、高徳院(鎌倉大仏)建立を支援するようになります。この大仏建立の目的は実ははっきりとしていません。
初代将軍 源頼朝が東大寺の大仏を再建した際、鎌倉にも同じような大仏が欲しいと望み、頼朝の妻 政子と侍女らがその意を継いだとする説。
また鎌倉幕府成立以降から続いた権力闘争の死者の怨霊を鎮めるため、浄土宗寺院の一つとして建造されたと考えられています。

1243年 鎌倉大仏は木造で完成しますが、4年後に暴風で倒壊したため、1252年に銅造で再建されます。
高徳院
鎌倉大仏は高徳院の本尊で青銅製の「阿弥陀如来坐像」。もともとは金箔が施されていたとされています。
高さ13メートル、総重量122トンで宋の影響を受けた仏像は、国宝に指定されています。もともとは、奈良の様な大仏殿がありましたが、後に津波で流されたため、現在の様に露座(屋根のない所にすわること)になったといいます。
得宗制度の始まり経時と時頼
1242年 北条泰時は病で亡くなります。泰時の嫡男はすでに亡くなっていたため、孫の経時(ほうじょうつねとき)が四代目執権になります。
北条泰時は亡くなる前、これまでの身内争いを懸念し、執権になれるのは嫡流のみとし、分家は本家を補佐するよう、得宗制度を作っていました。
しかし四代執権 北条経時はこの時まだ19歳で、やはり相続問題は起こってしまったのです。
この相続問題には豪族 三浦氏、北条氏分家名越氏、そして四代将軍 藤原頼経が含まれた大規模なものとなります。
四代将軍 頼経は成長してからお飾りの将軍に嫌気がさしていたようで、名越氏は北条氏の中で得宗家(本家)に次ぐ高い家柄の自負があり、それを三浦氏が利用したと考えられます。
しかし事前にその計画を察知した人物がいました。京で六波羅探題をつとめる二代執権義時の三男北条重時(しげとき)です。この頃の京の都では、貴族中心に様々な情報が流れていたようです。
京から急ぎかけつけた北条重時は、御所・三浦の館・名越の館を取り囲み、実の兄の名越氏を説得して計画を未然に防ぐ事に成功します。これはこれまでに二度得宗相続で起こった事件の経験が活かされていたのでしょう。
なんとか無事に執権となった北条経時は若さゆえから思い切りがよく、反執権勢力と化した四代将軍頼経を解任し、その子藤原頼嗣(ふじわら よりつぐ)を五代将軍に任命します。
しかし1246年 北条経時は23歳の若さで原因不明の病にかかり亡くなります。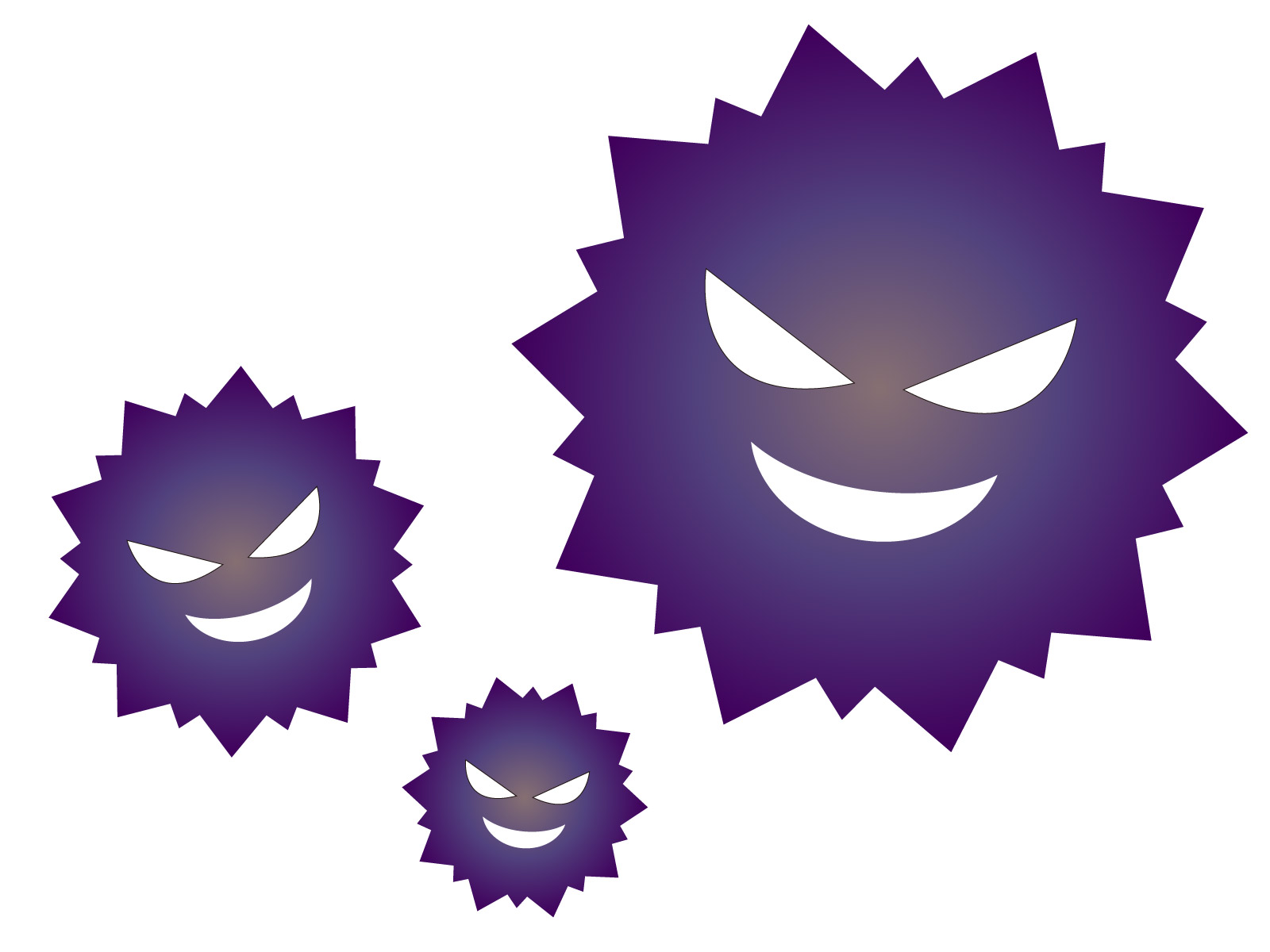
経時の子がまだ年少だったため、弟の時頼(ときより)が執権をつぐことになります。北条時頼はこの時20歳です。
蒙古軍の脅威
執権を継いだばかりの北条時頼には二つの難題が待ち構えていました。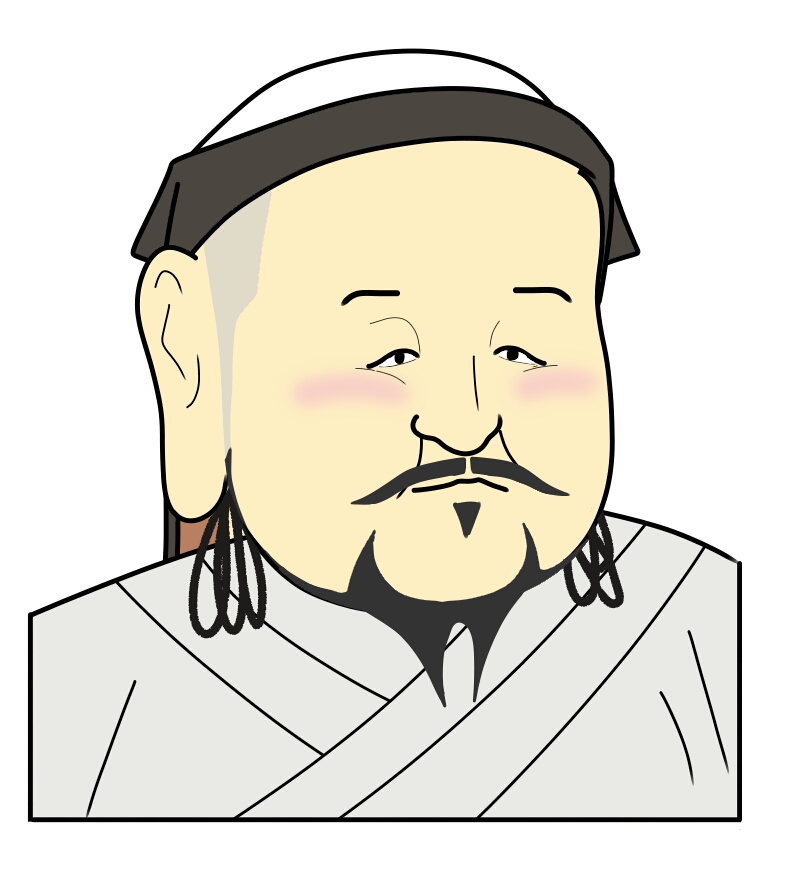
忽必烈(フビライ・ハン)
この時代では成吉思汗(チンギスハーン)から始まった蒙古の五代皇帝 忽必烈(フビライ)が、高麗(朝鮮)を属国にして南宋(中国)を滅ぼす勢いを見せていました。そして王朝名を元と称し、日本にとっても大きな脅威となっていました。
元はもともと遊牧民族のため、貿易や商売などの交易よりも侵略を優先し、その圧倒的な騎馬軍団で他国を従属させていました。そして南宋の次の標的が、海を越えた日本にされていたのです。
三浦合戦(宝治の乱)
さらに近々の問題として、これまで何度も謀反の兆しをみせてきた三浦氏が、軍備を整えて謀反の準備をしているという知らせが入ります。
この時の反執権勢力には、京の公卿九条氏(藤原氏)、前将軍の頼経、名越氏、三浦氏、毛利氏(大江広元の一族)、さらに源氏一門の足利氏までもが加わっていました。
北条時頼は入念な準備をし三浦氏の館を取り囲みます。この一触即発の状況において時頼は、三浦氏にこれまで同様和平交渉を行うように見せかけます。
そして三浦氏の油断をつき御家人の安達氏に急襲させたのです。不意をつかれて混乱した三浦氏は援軍を動員する事もできずに敗れたのです。
この戦で大豪族三浦氏(本家)は滅亡し、三浦氏分家がその後継となります。また源氏重臣の大江一族の毛利氏が討ち死にしています。
さらに時頼は謀反に加担していた将軍 藤原頼嗣とその後ろ盾の関白九条氏を辞めさせ、さらに源氏一門の足利氏当主を出家させ、領地の一部を没収しています。
北条時頼はこの先に控えている蒙古襲来の備えとして、早急にこのような争いの火種を消す必要があったので、反乱分子を根絶やしにする苛烈な手段を取ったのです。
なお北条時頼の正妻は毛利氏の出身だったためこの時に離婚し、御家人安達氏の娘と再婚して子が生まれます。北条時宗(ほうじょうときむね)誕生です。
その少し前に時頼の妾(めかけ)の子が生まれます。北条時輔(ほうじょうときすけ)です。時宗は本来次男ですが、正妻の子だったため嫡男とされたのです。
幕府念願の皇族将軍
1152年 鎌倉幕府は新将軍に後嵯峨上皇の皇子、宗尊新王(むねたかしんのう)を迎えます。鎌倉幕府に権威を必要とする北条氏にとって念願の皇族将軍です。(鎌倉幕府は朝廷から政権を簒奪したと世間にみられていたため、皇族の権威を欲していた。)
この頃に、敵対勢力の長九条道家(藤原氏)が亡くなり、執権北条氏は日本で最大の権限を持つ専制政治が実現したのです。
この頃首都機能はすでに京から鎌倉に移っていましたが、鎌倉には幕府が奨める仏教禅宗寺院がなかったため、北条時頼は禅寺の建長寺を建立します。この寺院は日本で最初の中国風修行専門道場となるのです。
建長寺
臨済宗建長寺派大本山で、鎌倉五山の第一位。中国の宋の禅宗の厳格さを取り入れ、境内は掃除が行き届いていて、それが建長寺の修行の厳格さを表しています。
立派な三門と本尊である地蔵菩薩、そして時頼が病に倒れた時に、快気を願って奉納された千手観音菩薩像があります。
北条時頼の政治
北条時頼の政治は質素倹約に勧め、鎌倉の市場価格(値段)を調整し、物の価格を上げすぎない物価統制を行います。そして鎌倉で疫病や天変地変が続いた際には炊き出しを行わせるなど、善政で農民たちを援助しています。
このように北条時頼は国内の体制を整えつつ蒙古対策に取り組んだのです。しかしその心労は大きかったのか、時頼は大病を患うのです。
1256年 病が癒えた北条時頼は隠居して出家します。時頼は隠居後に残った時を静かに過ごすため、最明寺に籠ります。しかし時頼は隠居してからも最明寺から、政権にアドバイスを行たっていため最明寺殿と呼ばれたようです。
嫡男の北条時宗がまだ年少だったため、代理として義時の孫にあたる分家の長時に六代目執権を務めさせ、その後は叔父で義時の子 政村に七代目執権を務めさせています。
そして若い頃から経験を積ませてきた分家の重時に、嫡男の時宗を支える様命じたのです。
1263年 北条時頼は37歳の若さで亡くなります。最明寺の敷地内にあった明月院が時頼の菩提寺となります。
明月院
明月谷にあり、1160年に創建され、時頼が建立した最明寺と同じ敷地にありました。そのため、現在も北条時頼の墓所と廟所が残ります。
方丈内の円窓は、悟りや真理、大宇宙などを円形で象徴的に表現したもので「悟りの窓」と呼ばれています。
また、鎌倉随一のアジサイの名所として有名で、満開時には約2,500株のヒメアジサイで境内が染まり、その淡い青色の花は「明月院ブルー」と呼ばれています。
北条時宗による新体制

1268年 北条時宗(ほうじょうときむね)を得宗(本家後継)とし、鎌倉幕府新体制が始まります。もちろん大きな課題は蒙古(元)対策です。
この頃には蒙古(元)襲来は世間で噂され、知れ渡っていました。その一因が日蓮(にちれん)の存在です。

日蓮は比叡山延暦寺で天台密教を学び、法華経が一番優れていると確信し、南無妙法蓮華経と唱えていました。これは悟りを開いた釈迦如来への感謝を表すものです。
一方鎌倉で民衆に広まった浄土宗は南無阿弥陀仏と唱えます。これは死後の極楽浄土を願う阿弥陀如来への信仰です。それぞれ信仰の対象が異なるのです。

釈迦如来 阿弥陀如来
日蓮は法華経を広めながら、鎌倉幕府に対してはげしく口撃します。日蓮は法華経を信仰しない幕府は他国からの侵略を受けると世間に触れ回り、この頃にすでに蒙古襲来を予言していたのです。
日蓮は鎌倉幕府から伊豆に流罪を命じられ、日蓮は罪が許された後も蒙古襲来を触れ回り、幕府への口撃を辞めなかったため、佐渡ケ島への流罪にされます。
しかし日蓮の、間違った行いには仏罰が起こるとする教えは、日蓮宗として地方を中心に世に広まっていったのです。
源氏将軍と執権時宗の誕生
いよいよ近づく蒙古襲来への備えとして鎌倉幕府は将軍の交代を行います。この頃には六代将軍は反執権勢力と係わるようになっていたのです。
そこで六代将軍を退位させその子惟康新王(これやすしんのう)を将軍にします。惟康新王はまだ三歳だったため、反執権勢力はしばらくおとなしくなると考えたのです。
将軍になる際惟康新王は天皇から源の性を与えられ、臣籍降下(皇族が臣下に降りる事)を行います。三代目将軍以来の源氏将軍の誕生です。
さらに幕府は北条時宗を執権に任命します。蒙古との大戦前に、得宗(本家)である時宗が執権に就いておくべきと考えたのです。これらはすべて蒙古対策として御家人たちを一つにまとめるために行われたのです。
1268年 蒙古の使者がとうとう日本に訪れます。その書状の内容は〝小国は大国に敬意を払うべし〟として、高圧的に国交を求めるものでした。
北条時宗は御家人たちを集め、武者の刀は天より与えられたもの、武者に生まれたことを誇りに思い、刀を持たぬものすべての盾となり、守らなければならぬと述べます。
今回の蒙古襲来は守りの戦のため、新たに領地は得られず、御家人たちに恩賞の期待をさせることはできませんでした。そこで御家人たちの考え方を改め、団結させる必要があったのです。
弟の謀反(二月騒動)
蒙古に対する返書をめぐり、無礼であるとはいえ国交すべきとする朝廷と、あくまで戦うのみとする幕府で、激しく意見衝突が起こりました。
これまで中国や韓半島の国々と国交してきた経験のある朝廷と、一度も国交の経験がない幕府の間で、意見が衝突いいたのは当然と言えます。その結果朝廷の意見は無視し、幕府の意見を押し通すことになったのです。
これに怒った朝廷の貴族等は、北条氏の名越氏(分家)や、京の六波羅探題の時輔(時宗の弟)らを唆し、反乱を起こさせて幕府の力を削ごうと考えます。
しかし事前に察知した北条時宗は、この反乱計画に加担する名越氏と北条時輔を討ち取ったのです。
北条時宗と時輔はもともと仲の良い兄弟だったとされます。しかし妾の子時輔は兄でありながら弟という扱いをされ、さらに当時の首都ではない、遠く離れた京にいる間に〝疎外感〟を感じ、この反乱に加わったと考えられます。
蒙古襲来
蒙古の襲来が近づき、北条時宗は御家人の借金をすべて免除する徳政令を行います。これは武士が借金で、刀や鎧の手入れもできない様では困るからです。もし蒙古軍に敗れたなら、借金どころかすべてを失う事を時宗は理解していたのです。
蒙古との戦いは九州の大宰府守護の少弐氏、さらに九州御家人の大友氏と松浦氏、そして幕府御家人の安達氏が中心となります。
北条時宗が提唱した作戦は、ゆるゆると戦いながら敵を船から内陸へと誘い込み、大宰府に隠した主力で一気に殲滅するというものでした。
これは敵を博多から逃さずに殲滅することで、侵略をあきらめさせるという狙いがありました。さらに水軍が中心の蒙古軍は得意の騎馬戦術が使えないため、時宗は十分勝ち目があると考えていたのです。
1274年 蒙古軍の大水軍は、対馬沖の広い湾を船で埋め尽くして現れます。そして対馬の御家人は全滅し、蒙古軍が上陸したのです。この時蒙古兵たちは非武装の島民まで殺害したとされています。
蒙古軍の総兵数は2万5千程とされています。それに対して幕府軍は主力を大宰府に隠す、少ない兵数の不利な状況で開戦します。
蒙古軍は鉄砲(てつはう=火薬玉の様なもの)を使い、さらに鉦(かね)や太鼓の音で戦術を伝達する連携した戦いを行います。それに対する幕府騎馬隊は、馬が鉄砲の音に混乱するなど苦戦を強いられたのです。

そこで幕府軍は蒙古軍を内陸の湿地帯に誘い込み、鉄砲(てつはう)が効果を発揮できくなったところで互角の戦いをみせます。幕府軍は少ない兵ながらよく戦い、蒙古軍を内地におびき寄せて一時撤退したのです。
戦場は博多に移り御家人達の戦意が落ち始め、大友氏のが大宰府に撤退を開始します。ところがここで蒙古軍は、全軍を船に撤退させてしまったのです。
蒙古軍は幕府軍の予想以上の手強さを感じ、何かしらの不安を抱いたのではないかと考えられます。
しかし船に戻った蒙古軍に、突然の大嵐が襲いかかります。そしてこの嵐に巻き込まれほとんどの船が沈んでしまったのです。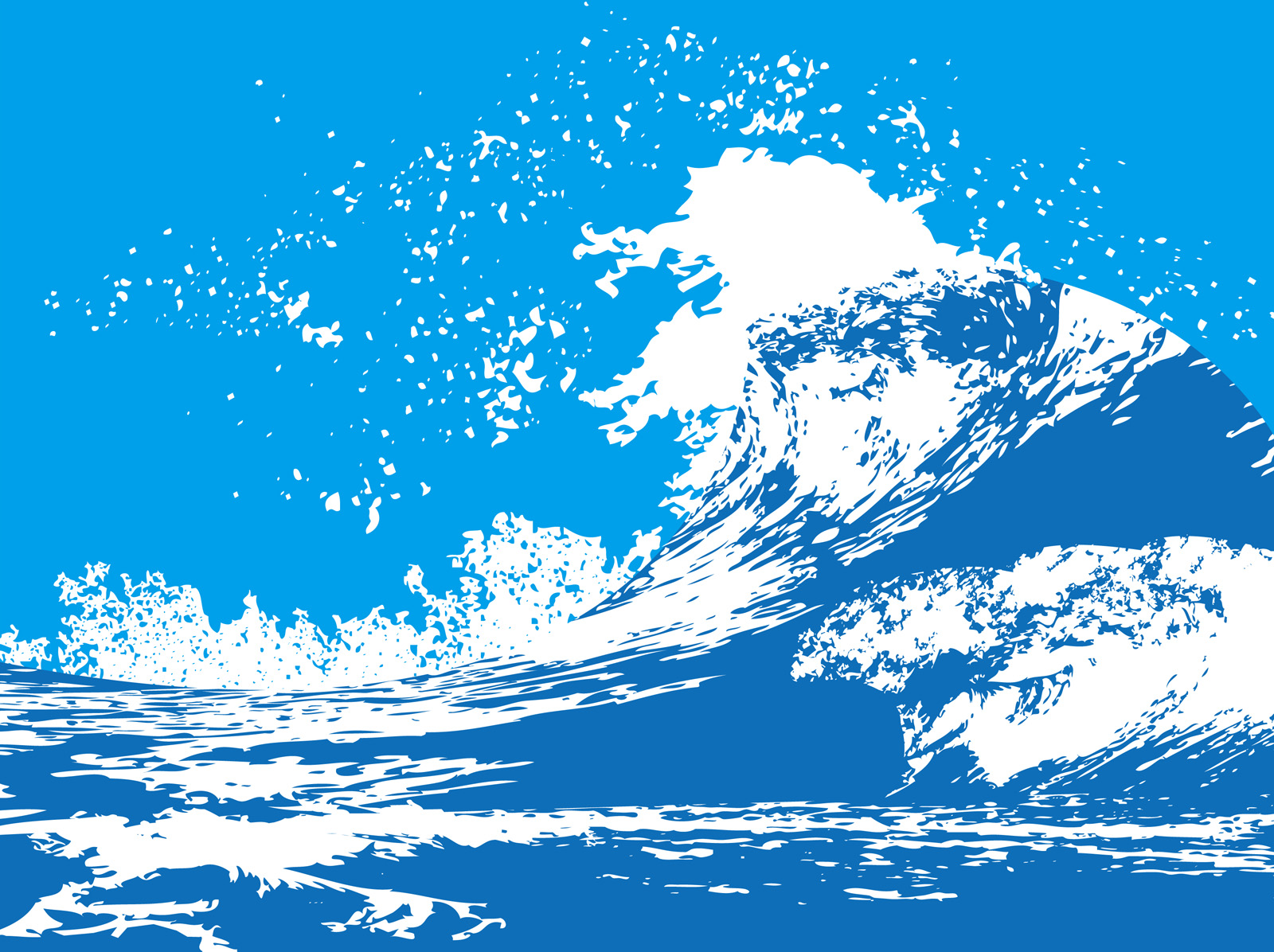
この結果に、京の朝廷や寺社は祈祷のおかげで神風が吹いたと主張しました。しかし幕府の北条時宗は勝因が嵐である以上、蒙古軍が再び襲来すると考え、危機感を募らせたのです。
北条時宗は九州を除く御家人から、資金を集めて敵を上陸させないための防備を整えます。これは多くの負担をかけた九州御家人に対する配慮です。
そして再び訪れた蒙古の使者は御家人たちの前で処刑します。これは御家人たちの戦意を高め、気を引き締める目的があったとされています。
この頃に北条時宗の叔父の金沢実時が病で亡くなり、さらに重鎮の北条政村も亡くなり、時宗は実質一人で蒙古対策の重責を背負うことになったのです。
二度目の襲来
博多で防衛のための石築地(石垣の堤防)が完成します。それらは延々と延び、威圧すら感じる堂々たる佇まいを見せていました。九州に時宗の弟北条宗政(ほうじょうむねまさ)が総大将となり、御家人の安達氏等が配置されました。
元寇防塁跡

1281年 蒙古軍が再び現れます。蒙古は約2万5千の朝鮮兵が中心で、壱岐に上陸し侵攻を開始します。しかしこれはあくまで第一陣で、南宋(中国)からはさらに10万の援軍が来るとの情報があったのです。
蒙古軍は援軍到着まで壱岐で過ごす予定でしたが、食料や水が不足したうえ、流行り病が流行し、待つことができず、援軍合流前に先制攻撃を仕掛けきます。
すでにその動きを予測していた幕府軍は、5万の大軍勢で待ち受け戦いを優勢に進めます。さらに合流予定の南宋軍が大幅に遅れたことで、蒙古軍は孤立します。
戦は壱岐の沖合で海戦となり、内地から補給のある幕府軍に対し、補給がない蒙古軍はじりじりと押されていきます。ようやく南宋軍が合流した頃には、蒙古軍は半分以下になっていたのです。
しかし援軍が合流した蒙古軍は三千艘もの大船団となり、幕府軍は一時撤退し大宰府からの援軍を待つことになります。
そしてこの時に再び大嵐が起こり、不幸なことに蒙古船団がいた平戸には、三千艘もの船を付ける湾が無く、ほとんどの船が大嵐の真っただ中にとり残されたのです。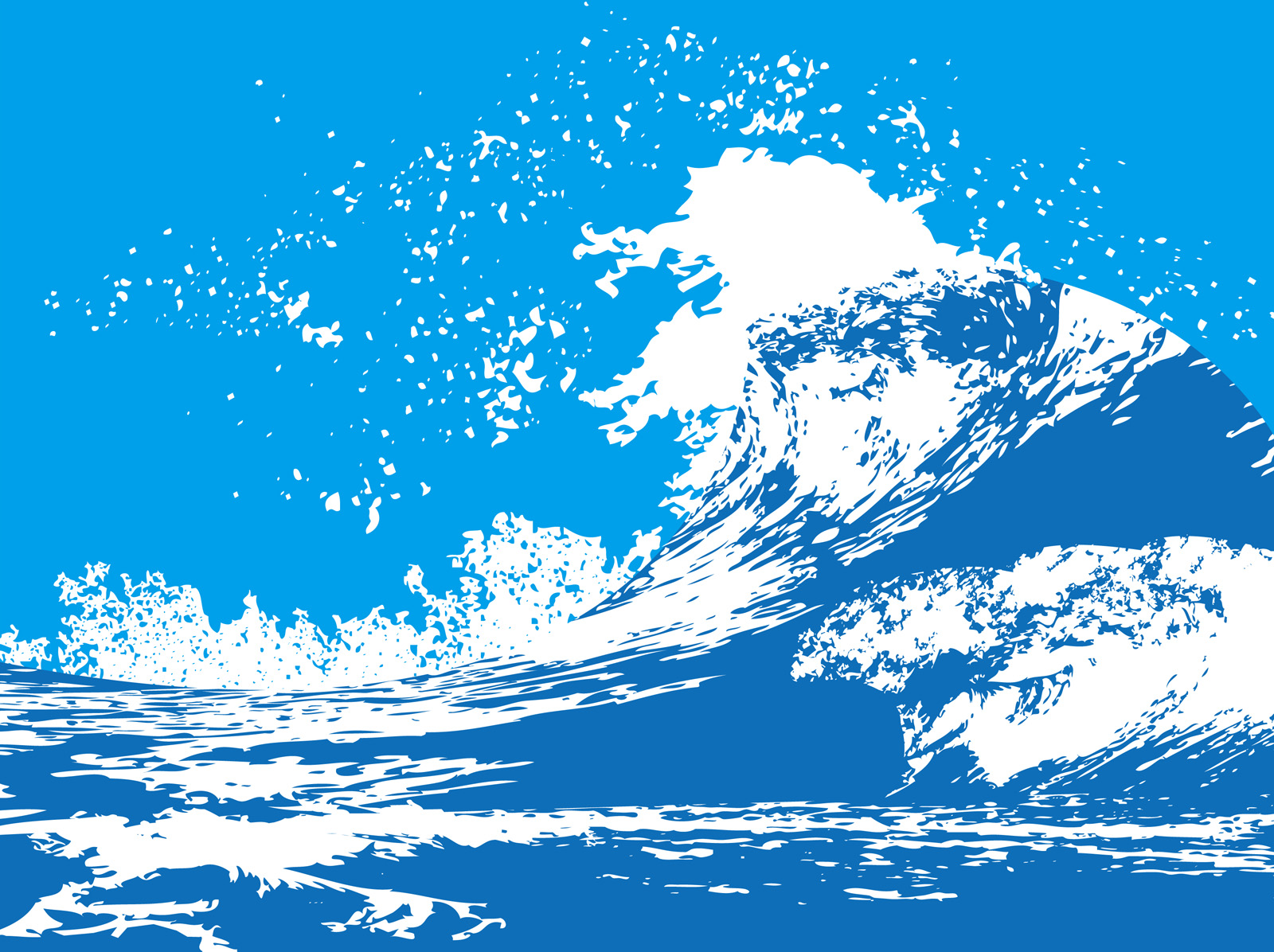
こうして蒙古軍の三千艘の船団は壊滅し、鎌倉幕府は二度目の蒙古軍を退けることに成功したのです。
しかし今回の戦も嵐のおかげの勝利だったため、三度目の襲来があることを予感した北条時宗と幕府は手放しに喜ぶことができなかったのです。
興味のあるかたはこちらもどうぞ!
中部観光ホームページ 歴史と共に巡る旅(鎌倉大仏、鶴岡八幡宮、明月院、建長寺)

コメント